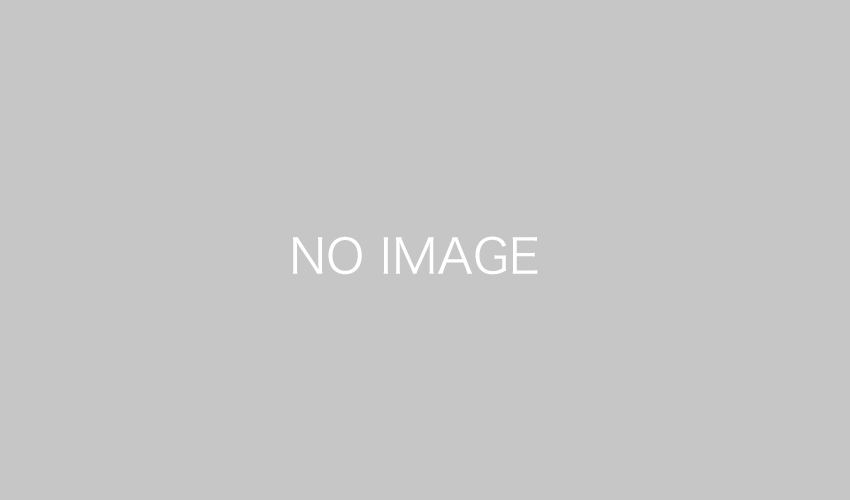許認可

承認取得までのスケジュール短縮と成功率向上を実現
日本の「薬機法(Pharmaceutical and Medical Device Act, PMDA Act)」では、日本国内で流通/販売される医療機器について、PMDAまたはRCB機関からクラス別に承認または認証が要求されています。
ただし同法第68条により、患者の治療目的で緊急に使用しなければならない場合は医師の責任で製品を輸入/使用することができますが、このような製品は商業的に販売することはできず、限られた患者の治療や研究目的でのみ使用する必要があります。
さらに、商業的に日本国内で流通・販売するためには、以下のような許認可手続きが必要です。
厚生労働省に承認、申請を求める申請書を作成し提出します。
臨床試験データおよびその他の資料は、厚生労働省令で定められた医療機器の臨床試験の実施の基準(GCP)に基づく「申請資料の信頼性に関する基準」に従って収集されたかどうかを徹底的に審査し、製品が科学的かつ倫理的に信頼できるものであり、試験が試験計画書に従って実施されたことを確認します。
製造所の調査は、「製造供給能力があるかどうか」「品質管理が適切であるかどうか」を判断することを目的としています。
今後「安定的に製品を製造・供給し続けられるか」を確認するための調査です。
このような厳格な審査を経て、厚生労働大臣と審議会を経て承認を受けることとなります。
クラス別承認/認証の種類と審査機関
| 医療機器の分類 | 種類 | 審査 |
|---|---|---|
| クラスⅣ(高リスク):高度管理医療機器 不具合が生じた場合、生命の危険に直結する恐れがあるもの (例)ペースメーカ、人工心臓弁 |
承認 (一部認証あり) |
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 (PMDA) |
| クラスⅢ(中リスク):高度管理医療機器 不具合が生じた場合、生体へのリスクが比較的高いと考えられるもの (例)透析器、人工骨、人工呼吸器 |
||
| クラスⅡ(低リスク):管理医療機器 不具合が生じた場合でも、生体へのリスクが比較的低いと考えられるもの (例)MRI、電子内視鏡、消化器用カテーテル |
認証 (一部承認あり) |
第三者認証機関 (ARCB) |
| クラスⅠ(極低リスク):一般医療機器 不具合が生じた場合でも、生体へのリスクが極めて低いと考えられるもの (例)X線フィルム |
届出 |