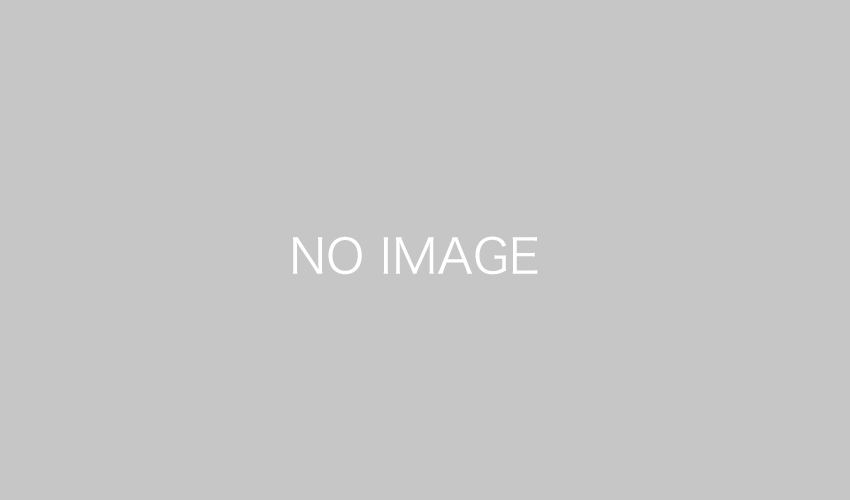保険収載

費用対効果データや臨床的有用性の証明が求められる
日本の医療保険制度の仕組みは以下の通りです。

図1 日本の医療保険制度の仕組み(JOMDD作成)
日本の保険制度では、保険診療を行った場合に医療機関がその報酬として請求できる金額が定められており、この報酬を「診療報酬」といいます。
診療報酬は、厚生労働大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)の意見を受け、厚生労働大臣が決定します。原則として2年ごとに診療報酬は改定されます。
この診療報酬は、主に診療行為(サービス)を行った対価である「技術料」を指します。診療報酬が本体以外の部分としては、物品の価格が別途設定されており、診療行為に伴って使用した医療材料(医療機器)の価格として「特定保険医療材料」があります。
日本の保険区分は以下の通りです。
A1(包括)
既存の診療報酬項目において包括的に評価 (例:縫合糸、静脈採血の注射針)
A2(特定包括)
既存の特定の診療報酬項目において包括的に評価 (例:超音波検査装置と超音波検査)
A3(既存技術・変更あり)
当該製品を使用する技術を既存の診療報酬項目において評価
B1(既存機能部分)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価 (例:冠動脈ステント、ペースメーカー)
B2(既存機能部分・変更あり)
既存の機能区分により評価され、技術料とは別に評価 (機能区分の定義等の変更を伴う)
B3(期限つき改良加算)
既存の機能区分に対して期限付改良加算を付すことにより評価
C1(新機能)
新たな機能区分が必要で、それを用いる技術は既に評価 (例:特殊加工が施された人工関節)
C2(新機能・新技術)
当該製品を使用する技術が未評価 (例:リードレスペースメーカー)
※B3, C1, C2は中医協における了承が必要な評価区分
出典)中央社会保険医療協議会保険医療材料専門部会「保険医療材料制度の見直しに関する検討(その1)について」(2023年9月20日)